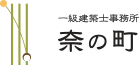奈の町の家【奈の町の家14の話】
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Contents
【奈の町の家14の話】
奈の町が住まい手さんにご提供できる提案や約束、決めごと等をご紹介しています。
これらは、一つしかない住まいを建てる上で、奈の町が住まい手さんをサポートする為のとても大切なポイントだと考えています。14の話を読んで頂けると幸いです。 【2023年改訂】
✔第1の話 ◆奈の町が「住宅設計専門」へのこだわり
私が最も興味を持ち、大好きなのは『人が暮らす住まい』です。住まいは、住む人の想いの結晶であり、唯一安らぎを感じ流ことのできる場所です。私は、この住まいの設計こそが天職だと深く感じています。住まい手さんの笑顔を見ることは、私の喜びであり、そこから一般個人の住まいに特化する方向を選びました。
✔第2の話 ◆一般個人しか受注しないのは?
私は、業者(建築施工会社、住宅販売会社、不動産業者を問わず)からの受注を受け付けていません。その理由は明確です。業者からの仕事を受けた時点で、私と業者の間に元請けと下請けの関係が生まれてしまいます。この関係性が出来上がってしまうと、住まい手さんのために100%の努力をすることが難しくなります。確かに、一般家庭だけの受注にこだわる経営は厳しい面があるかもしれませんが、私が住まい手さんの側に立つ専門家としての信念は曲げられないのです。
✔第3の話◆家具のオリジナル製作について。
新しい住まいを設計する際、すでにお持ちの家具の情報は大切にしています。そして、奈の町としては、多くの家具をオリジナルで設計・製作しています。
食器収納や吊棚は当然、ご希望があればキッチンまで手がけます。大きな家具としては、洗面所の収納やTVボード、下駄箱やダイニングテーブル、ベンチなど。小さなアイテムでは、ポストやタオル掛け、玄関ベンチや引き出し収納、姿見鏡や独自デザインの手摺まで。どこにも販売されていない、奈の町オリジナルの木製家具を提供しています。
ぜひ、この視点で奈の町の家を体感してみてください。小さなディテールにも、当社のオリジナリティが息づいていることを感じていただけるはずです。
✔第4の話 ◆『設計ステップノート』を活用した設計の進め方。
奈の町オリジナルの「設計ステップノート」を使用することで、住まい手の方々が設計の各ステップを理解しながら家づくりを楽しむことができます。各ステップにはイベントが設定されており、事前に情報を学ぶことや、感じたことをメモすることが可能です。このノートは、次回の打ち合わせをより楽しみにしてもらうためのものです。
✔第5の話 ◆3Dレンダリングやクラフト模型を活用して理解を深める。
建物の形状や空間を言葉だけで伝えるのは難しいです。そのため、奈の町では3Dレンダリングやクラフト模型を使用して、設計の概念を実際に目で見て、手で触れることで感じていただくことを重視しています。これは、実際のスケールや空間をリアルに体感するためのツールとして使用されます。そして、クラフト模型は計画段階での制作ですから設計完了時は更に進化し、より使い勝手の良い住まいへとなっています。
※ 製作したクラフト模型は設計が終了しましたら住まい手さんにプレゼントさせていただきます。
✔第6の話 ◆木造構造へのこだわり。
現行の建築基準法では、木造二階建ての建物に対する構造計算の義務はありません。しかし、私たちは安全性を最優先に考え、2005年からこの計算を実施しています。2025年4月からは、2階建て住宅の新築や大規模な修繕、模様替えにおいても構造計算及び構造図が義務化されます。
※1 新築時のすべての工事において、標準として構造計算を実施しています。この計算は、地震時の柱や梁の変形を予測し、適切な部材や金物を選定するものです。
※2 リノベーションやリフォームの設計では、精密な耐震診断を実施し、耐震補強計画を策定します。そして、安全ラインである評点1.0以上を目指します。
✔第7の話 ◆構造材として奈良の吉野材を採用。
日本三大美林の一つ、吉野材はその強さと美しさから高く評価されています。奈良で生産されるこの上質な材木は、奈良の気候で育ったもの。それだけに、奈良での家造りには、吉野材を使用することが最も適していると感じています。近年、多くの施工会社が吉野材を採用するようになりましたが、奈の町としては2008年の完成物件から現在まで、一貫して吉野材を使用し続けています。使用する部材に関しては、柱、土台、大引、筋交い、間柱、垂木は全てヒノキを、梁、小屋束、母屋は杉を採用しています。
✔第8の話 ◆住まい手の設計図を全て作成
住宅には住まい手の想いが詰まっています。その想いを形にするためには、単なる平面図や立面図では不十分です。ですので、奈の町では具体的な図面を全て作成し、施工会社へとその想いをしっかりと伝えています。
✔第9の話 ◆施工会社の選定は”シームレスビルト方式”を採用。
奈の町では、建築費用の高騰を受け、独自の”シームレスビルト方式”を採用しています。この方式は、住まい手と設計者で住宅の基本計画や求める性能を決定した後、最適な施工会社を選び、3者で細部の仕様を施工レベルまで詰めて打ち合わせを行う方式です。これにより、建築予算を超えることなく、プロジェクトを進めることが可能となります。さらに、見積もりが早く出せるため、融資の申し込みもスムーズに進行します。この方式のもう一つのメリットは、早い段階から施工会社の担当者との打ち合わせが始まるため、深い信頼関係を築くことができる点にもあります。
✔第10の話 ◆工事代金の請求はすべて奈の町を経由。
工事代金のトラブルとしてよくあるのが、追加工事費です。発注者と受注者の間で、「追加だと理解していた」とか「追加工事だとは思っていなかった」という認識の違いが生じます。
奈の町では、追加と判断される内容(設計図に記載されていないもの)については、必ず見積もりを取り、建築主に確認後に発注します。すべての請求書は当社を経由して届き、もし工程が進んでいない場合には当社で留め、問題がなければ住まい手に転送します。したがって、当社の経由印のない請求書は、住まい手が支払う必要はありません。このように、当社が間に入ることで、不明瞭な請求や支払い過剰を防止しています。
✔第11の話 ◆家づくりの時間感覚。
設計から完成までの期間はおおよそ1年です。この1年を長いと感じるか短いと感じるかは、家づくりを体験する前と後で異なります。家づくりの過程は楽しいもので、初めは「完成まで1年も待たないといけないのか」と感じるかもしれませんが、工事の終盤になると「もう終わるのが寂しい」という気持ちになることも。実際、家づくりを楽しんだ後、宝くじが当たれば「もう一度家を建てたい」と言って頂ける方もいます。家づくりは楽しみながら進めるべきもので、それが3ヶ月やそこらで終わるなんてのは楽しめなくてもったいないと思います。
✔第12の話 ◆現場監理の頻度。
現場監理は、設計者も住まい手もとても重要視する業務です。計画通りに進行しているかの確認が不可欠だからです。奈の町では、特に重要なポイントでの現場監理を実施しています。具体的には、基礎配筋時、床の処理、断熱材充填時、耐震補強や金物検査、屋根の検査と防水処理、内部仕上げの確認、建具周り、家具の確認、給排水、照明の位置確認、サッシや排水処理などで、現地での監理を行います。多くの監理が必要ですが、これにより現場の進行をしっかりと把握し、問題を速やかに解決することができます。
✔第13の話 ◆住い手さんに現場への参加をお薦めしています
私が監理のために現場へ行く際、住まい手さんを同行してもらいたいと感じることがよくあります。監理のスケジュールに合わせて、現場の進行を直接確認していただきたいのです。職人の技術を実際に目の当たりにすれば、規格型の家とは異なる、自分たちだけの暮らしに合わせたオーダーメイドの住まいを感じていただけると思います。
✔第14の話 ◆奈の町での家づくりのサポート。
奈の町では、住まい手の家づくりに関する様々な要望や夢を大切に考え、実現のお手伝いをしています。その中で、多くの住まい手さんから「奈の町の家が好きだから、土地や物件の購入から家づくりの相談にのってほしい」との声を頂戴しています。また、中古住宅の購入を検討されている方から「リノベーションしたい」というご希望も寄せられています。
実際のところ、物件探しを始める前に一度ご相談いただくことが、非常に大切だと感じています。その理由は、お客様のライフスタイルや価値観をうかがいながら、適切なアドバイスや提案をすることができるからです。予算に関しても、物件価格、建築費用、その他の経費、さらに設計予算などを総合的に考慮して、一緒に計画を立てることが可能となります。
過去には、先に物件を購入された後でのご相談もありました。しかし、残念ながらその場合、ご希望通りの家づくりが難しいとお伝えすることになりました。

実は近年、建築費は急激に上昇しており、その影響を受けやすいのが現実です。だからこそ、最初から予算の計画をしっかりと立て、その上で適切な物件選びをすることが大切だと考えています。
もし、奈の町での家づくりをご検討の方がいらっしゃいましたら、物件選びの前に、まずは一度ご相談にいらしてください。共に、理想の家づくりの計画を練り上げていきましょう。
奈の町でのサービスとしては、住宅に関するコンサルティングや予算の策定、物件のチェック、中古住宅の診断、仲介サービス、そして住宅設計に関するアドバイスなど、家づくりに関するあらゆる相談をワンストップで受け付けています。
2023.1.16【2023年改訂】
古民家リフォームについて

一般に、古民家とは60~70年以上前に建てられたもので、建物の構造は木造ですが、基本的に異なるのはその工法です。
現在の在来工法とは異なり、伝統的軸組工法という構造です。
材料も比較的大きな材料が使われていて、メンテナンスさえしっかりしていれば200年以上持っている家もあります。
実際、奈の町でも築250年の古民家をリフォームさせていただきましたが、構造は意外にしっかりしていました。
しかし、なにぶん長い時間が経過していますので、建物のひずみや柱の傾斜や沈下、木材の腐り、白アリ被害等は彼方此方にありました。
こういった古民家を、本格的に創建時の形へ修繕改修し、さらに耐震補強をするならば、膨大な費用が掛かることを皆さんあまりご存じないのではないでしょうか。
古民家を本格的に改修すると、新しい家が建つくらい掛かります。
古民家を購入してから改修を考えておられる方は、この費用を考慮せずに購入すると、買ったとたんに資金ショートということになりかねません。
既に古民家をお持ちの方も、高額のな修繕等はできませんよね。
例えば建物の補強は、どの程度の工事になるでしょう。
基礎について見てみます。
古民家は束石の上に乗っているものですから、いわゆるコンクリート製などの基礎を持ちません。 基礎を新たに設置するには、本体を空中に浮かせ(揚げ家工事)、下部に基礎を作ります。 また、古い建物は、建物の自重や地盤の状態で各柱ごとにバラバラに沈下が起こっています。
これを地面から安定させるためには、建物の下にある地盤そのものを補強する必要があります。
それこそ、全体をばらして地盤から手を入れることになります。
現実には、そんなことまで出来ませんよね。
さて、限られた予算を、いかに有効に使うか。
古民家改修の極意は、どこまでを改修できるのかということを住まい手自身が理解した上で、納得できるラインを決めること。
これに尽きます。 全部せずにどこまでで改修の線を引くか、ということですね。
始めに建物を調査する事から始まります。 傷んでいるところ、補修の必要なところを具体的にリストアップして、その補修費を算出します。
さらに、そのリストの各項目を、「絶対修繕の必要なもの」から「修繕は次回改修時に延期」まで、必要度合いによって数段階に分けます。 その上で、優先順位の高いものから順に補修費用の予算枠を採ってゆくのです。
予算の上限はご自身でご存じですよね。 合計してゆくうちに予算が尽きた所が、今回の補修範囲となります。
この方式なら、改修費用が500万だとしても、1000万、1500万、2000万としても納得してラインを引くことができるはず。
そのために絶対必要なのが、各工事の項目ごとの概算なのです。 それがリスト化できれば、自分達の方向性がぶれることなく、目的が達成できるという訳です。
ここで、忘れてはいけないことが3つあります。
1つは、予算の都合で出来なかった工事は次期に回しても必ず行うこと。これを事前に理解しておきましょう。
建物は古いので、必要な工事は後日必ず行うことをお勧めします。
2つめは、工事内容のリストに、楽しみのための費用を含めておくことです。
補修リストの他に必要なリスト。暮らし易い、またはこだわりを実現するための工事リストです。これを忘れてはいけません。
この別費用が、暮らしの潤いだったり、こだわりだったり、楽しみだったりするわけです。 補修リストの内容とあわせて、優先順位をつけましょう。
項目の中に入れておけば、予算不足を起こすことなく改修範囲を決めることができます。
3つめ、改修工事について忘れてはいけないことがあります。 それは追加工事について。
新築工事と異なり、改修・補修工事では、工事を進めるうちに補修を行うことで効果の大きく見込める部分や、雨漏り、白アリ等で必ず修繕を行う必要のある部分が出てきます。 そのような工事に備えるため、工事費の5~10%程度を見込んでおく必要があることを心に留めてください。 現場で発生した必要修繕工事は、費用対効果が高いものです。 このまま目をつぶって蓋をする選択肢はありますが、やはり後に回す方が割高な結果になりますから修繕しておくことをお勧めします。
LINK